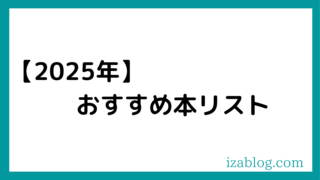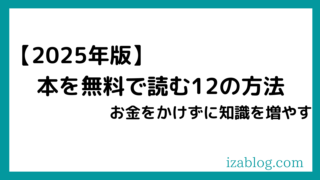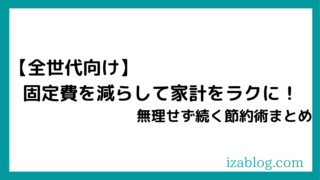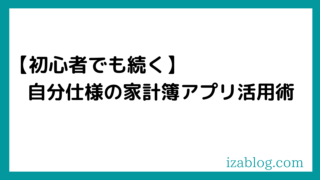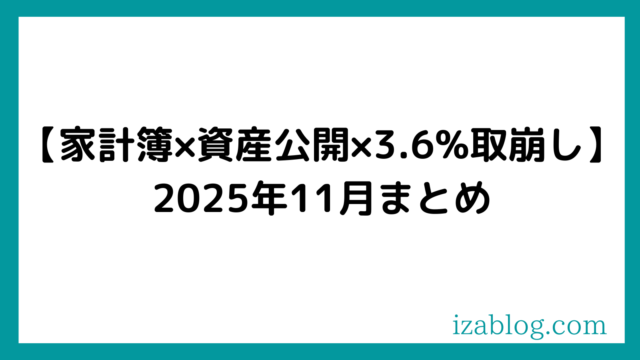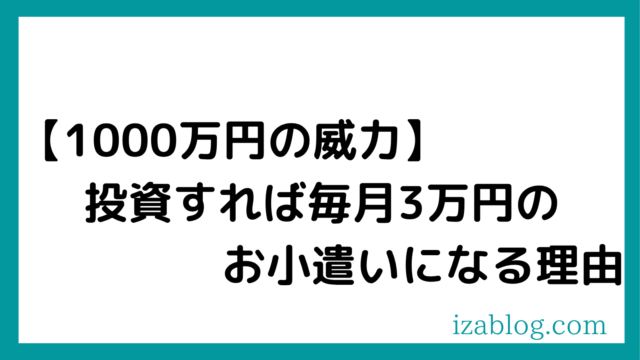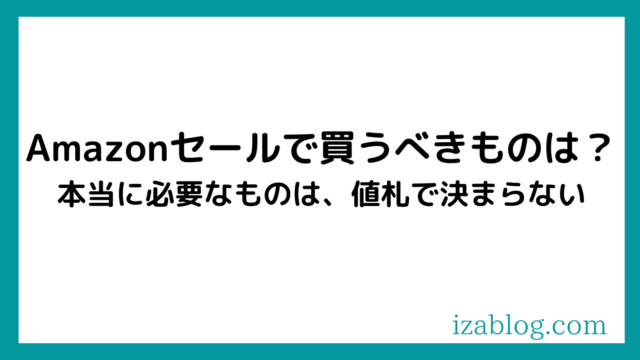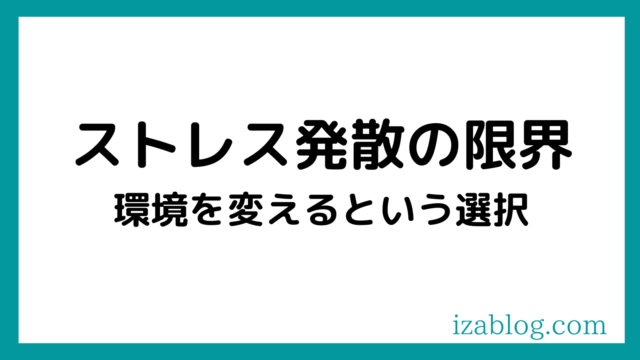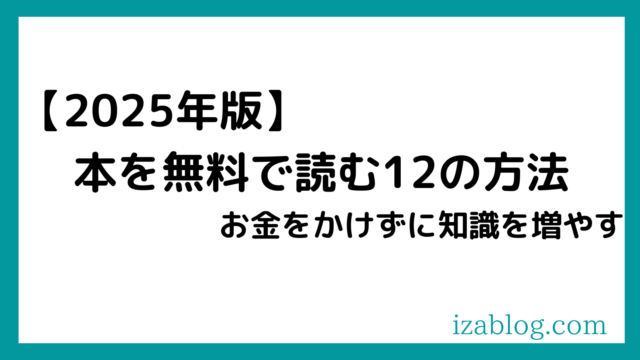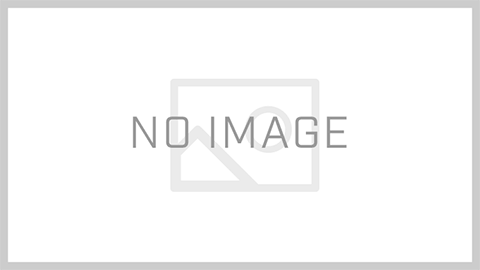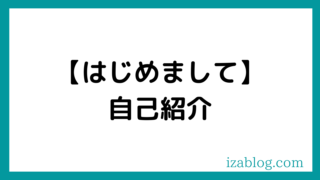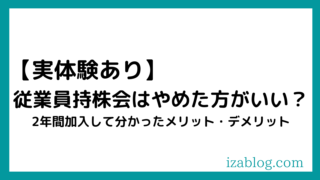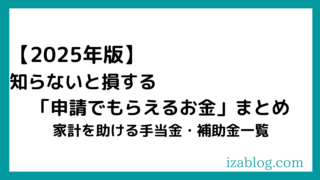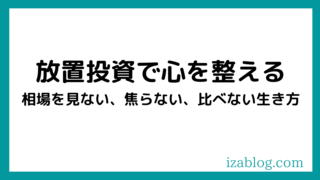【2025年版】知らないと損する「申請でもらえるお金」まとめ|家計を助ける手当金・補助金一覧
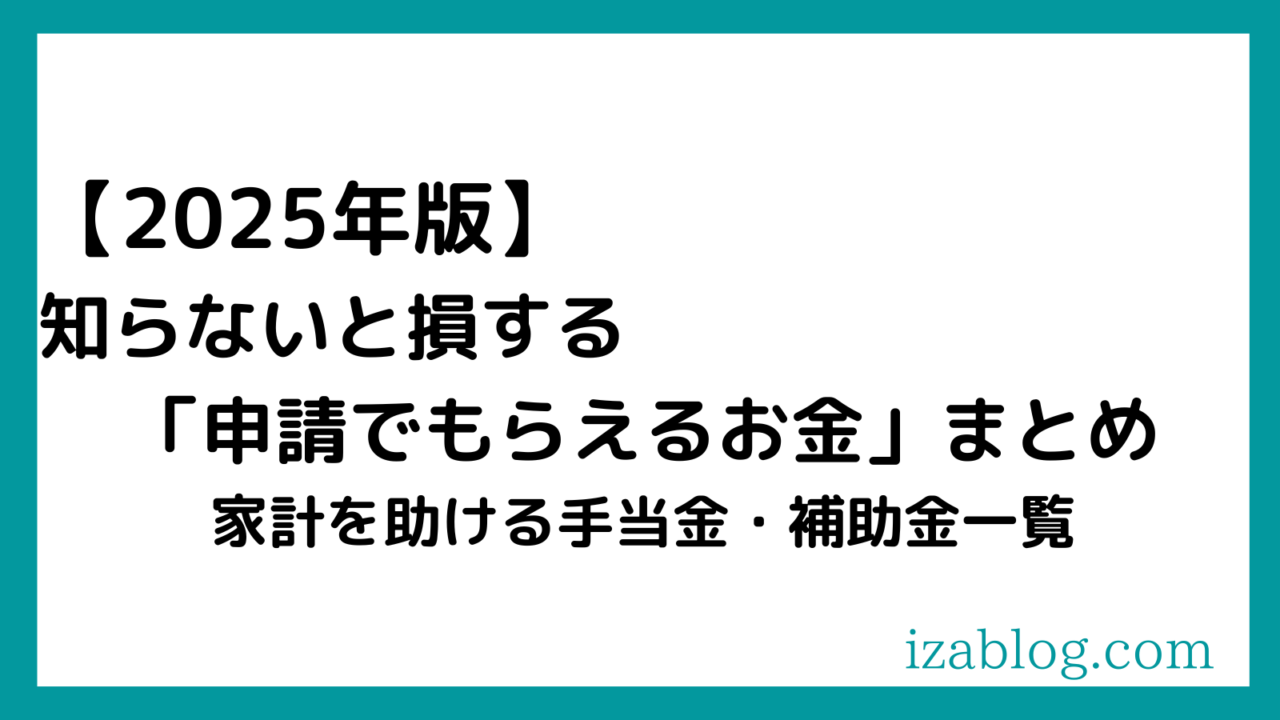
家計を見直すときに忘れがちなのが「申請すればもらえるお金」。
国や自治体には、条件を満たすだけで支給される制度がたくさんあります。
今回は、節約・家計改善の視点から、生活の負担を減らす制度をわかりやすくまとめました。
いざです。X(Twitter)、Youtube やってます。
【お問合せ・自己紹介】
生活を助けるお金(全世帯向け)
高額療養費制度
同一月に支払った医療費の自己負担額が高額となった場合、上限以上に支払った金額が後から払い戻される制度。
| 条件 | 上限額は年齢や所得によって変わる |
| 実費負担例 | 69歳以下、年収370万円までだと57,600円 など |
※これがあるので、我が家では民間の医療保険は契約していません。
医療費控除
1年間で一定金額以上の医療費を支払った場合に所得税が軽減される制度
| 条件 | 1年間の医療費が10万円を超えた時 確定申告が必要 |
| 支給例 | 年収400万円 医療費20万円の場合 10万円×税率 だいたい2万円くらい戻ってくる |
| 注意点 | 領収書・明細書の保管を忘れずに |
セルフメディケーション税制
市販薬の年間購入額が12,000円を超えると所得控除対象。
OTC = 処方箋なしで買える医薬品。
| 条件 | 健康診断を受けている 確定申告が必要 |
| 支給例 | 年収400万円で年間5万円OTC薬品購入した場合 3.8万円×税率 だいたい11,400円くらい戻ってくる |
| 注意点 | 領収書は保管しておく必要がある 医療費控除制度と併用不可 |
人間ドック費用の助成制度
病院で人間ドックを受けると一定額の助成金が受けられる
| 条件 | 国民健康保険に加入(保険料を完納している) 年齢は40歳以上 |
| 支給例 | 人間ドック費用の半額程度 2万円前後の自治体が多い |
ガン先進医療利子補給制度
ガンの先進医療を受ける患者とその家族の経済的な負担を減らす制度。
ガンの先進医療の治療費の融資を受けた場合、その利子が補助される。
| 条件 | 患者本人が課税総所得600万円以下の世帯に属する 借入限度額300万円以下 借入利率5〜6%以内 |
| 給付期間 | 最長7年間 |
妊娠・出産・子育てで受けられるお金
妊産婦医療費助成制度
妊娠中に保険が適用される医療費については、その大部分を自治体が補助してくれる。
| 条件 | 妊娠の届出月〜出産日の翌月末までの妊産婦 |
| 支給額 | 自己負担が月額500円 |
| 注意点 | 実施している自治体としていない自治体があるので要確認 |
出産育児一時金
出産の際に手当金が支給される制度。
病院が直接受け取る「直接支払制度」を利用し、差額を払うのが一般的。
| 条件 | 健康保険に加入していること |
| 支給額 | 子供1人につき42万円 |
出産手当金
会社員・公務員が出産のために休む期間、給与の約3分の2が支給されます。
| 条件 | 産休中に給料が減る場合 健康保険に加入していること |
| 支給額 | 標準報酬月額の2/3 |
| 支給期間 | 最長で98日 |
育児休業給付金
育児休業中、給料の67%(6か月以降は50%)が支給。
ハローワークで手続きが必要です。(会社員なら会社経由で対応してくれます。)
| 条件 | 雇用保険に加入 男性でも可能 |
| 支給額 | 最初の180日間 賃金の67% 181日目以降 賃金の50% |
児童手当
中学生以下の子どもがいる方に支給される手当。
| 条件 | 自治体に申請 申請した翌月から支給可能 |
| 支給額 | 2歳まで 15,000円 中学生まで 10,000円 第三子以降は小学生まで 15,000円 |
| 注意点 | 所得制限限度額に該当すると満額もらえなくなります |
児童扶養手当
シングルファザーやシングルマザーが貰える手当金。
| 条件 | 所得による制限がある 子供の人数により変動 児童手当と両方貰える |
| 支給額 | 1人目 最大43,160円 2人目 最大+10,190円 ※子供2人で最大53,350円 3人目 最大+6,110円 |
| 支給期間 | 子供が18歳になるまで |
子ども医療費助成
通院・入院時の自己負担を軽減する制度。
高校生まで無料の自治体もあります。
| 条件 | 健康保険に加入 0歳〜15歳まで |
| 助成内容 | 自治体により様々ですがほぼ自己負担0円 月額の自己負担500円〜1,000円など |
| 注意点 | 予防接種費用、健康診断費用などは自己負担 |
出産祝い金・新生児支援
一部自治体では出産祝い金(1〜10万円程度)を支給。
| 条件 | 出産証明書と健康保険証を役所に提出 |
| 支給額 | 自治体によって違うので調べてください |
子育てファミリー世帯住居支援
子育てファミリー世帯向け。
月3万円の家賃補助 × 最長5年 など。
教育・進学で受けられるお金
就学援助
経済的に厳しい小・中学生の保護者を対象に、学校で必要なお金の一部を援助する制度。
| 条件 | 世帯全員の所得合計額が基準以下 子供の年齢や人数により様々 |
| 助成内容 | 学校用品、クラブ活動、修学旅行などの費用 健康診断の結果、治療が必要な疾病の費用など |
| 助成金 | 自治体による |
高等学校等就学支援金
家庭の経済状況に関わらず進学の機会の平等を目指し、高校の授業料が国に援助される制度。
| 条件 | 世帯年収の上限がある(年収910万円未満) 受給できるかは学校に相談が必要 |
| 助成金 | 公立 年額118,800円 私立 年額396,000円 |
| 注意点 | 授業料のみ |
高等教育の就学支援
大学・専門学校などで、授業料免除+給付型奨学金を利用可能。
JASSO(日本学生支援機構)で確認できます。
| 条件 | 受験を控えている高校三年生 大学&短大等に在学中で経済的な問題が発生 家庭の世帯収入による制限がある |
| 助成金 | 入学金と授業料免除 給付型の奨学金 |
| 支援例 | 私立大学に自宅外から通う場合 授業料の免除最大70万円+給付型の奨学金最大91万円 合計最大161万円/年 |
仕事・休職・失業で受けられるお金
傷病手当金
会社員が病気や怪我で長期間休んだ時に支給される
| 条件 | 業務外で発生した病気や怪我 病気や怪我が原因で仕事に就けない 仕事に就けず休んだ期間が連続3日を含んだ4日以上ある 休んだ期間に給料の支払いがない |
| 支給額 | 標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3 × 休んだ日数 |
| 支給期間 | 最長1年6ヶ月 |
僕は30代の時に2回、合計7ヶ月休職しましたが、
この制度のおかげで無収入にならず今日まで生き延びられました。
失業給付金(雇用保険)
失業した人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職ができるよう支援するための制度。
| 条件 | 直近1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上 ハローワークで申請する 自己都合は退職してから3ヶ月経たないと貰えない |
| 支給額 | 賃金日額 × 給付率(50〜80%)×給付日数(90日〜150日) |
職業訓練受講給付金
職業訓練を無料で受けながら職業訓練受講給付金として月10万円と交通費が支給される制度。
| 条件 | 雇用保険被保険者でないこと 本人収入が月8万円以下かつ世帯収入が月25万円以下 世帯全体の金融資産が300万円以下 |
| 支給額 | 月10万円と交通費 |
| 支給期間 | 最大で6ヶ月 |
| 注意点 | 審査があり倍率は時期によって変わる(必ず貰えるという訳ではない) |
介護休業給付金
家族の介護のために仕事を休業する際、給与の67%が支給される制度。
| 条件 | 雇用保険の被保険者 介護のために2週間以上休業 休業中の給料が休業開始前の80%未満であること |
| 支給額 | 休業開始賃金日額 × 支給日数 × 67% |
| 支給期間 | 通算して93日分 最大で3回まで分割可能 |
倒産時の未払い賃金立替払制度
勤務先が倒産し、賃金の未払いがあった時に、国が代わりに一部を払ってくれる制度。
| 条件 | 法律上または事実上の倒産が認められる 正社員だけでなくパートも請求可能 |
| 支給額 | 最大で未払い賃金の80% |
| 支給期間 | 最大で6ヶ月分 |
住宅・生活再建で受けられるお金
住宅ローン控除
住宅購入の際にローンを組んだ場合、ローンの年末残高の0.7%を所得税、住民税から差し引いてくれる制度。
| 条件 | 年間所得2,000万円以下 自分が住む用の家の購入(中古も可) 床面積が50平米以上 |
| ローン残高上限 | 3,000万円 |
| 備考 | 金利を0.7%以下で借りれば実質金利は無料 最初の年は自分で確定申告が必要 2年目以降は会社が年末調整でしてくれる |
結婚新生活支援事業
新婚生活のスタートを国が応援してくれる制度。
これから結婚を考えている方は、必ず自治体のホームページで確認してください。
| 支給条件 | 夫婦どちらも39歳以下 世帯年収が540万円未満 |
| 支給額 | 30万円か60万円 |
| 使い道 | 新居の購入費 新居の家賃など 引越し費用 |
住居確保給付金
失業や収入源で家賃が払えない時、国が代わりに家賃を支払ってくれる制度。
| 条件 | 離職&廃業して2年以内 貯金100万円以下 |
| 支給額 | 原則3ヶ月(最大9ヶ月分) |
| 注意点 | 自治体により上限額あり |
耐震・バリアフリー改修補助
住宅の耐震化・リフォームに対して補助金や税控除あり。
| 条件 | 3階建てまでの戸建木造住宅 市民税等の滞納歴がない人 |
| 支給額 | 工事費用の10%を所得税から控除 20万円〜50万円の現金支給 |
被災者生活再建支援制度
自然災害により住宅の全壊等の被害を受けた世帯に支援金を支給し、生活の再建を支援する制度。
| 条件 | 自然災害により住宅が全壊or半壊した世帯 一定規模の補修が必要な世帯 |
| 支給額 | 全壊で100万円 半壊で50万円 + 家の建築、購入で200万円 家の補修で100万円 賃貸住宅の引越しで50万円 |
災害弔慰金支給制度
自然災害が原因で亡くなってしまった場合に遺族が受けられる。
| 支給額 | 生計を維持していた人 最大500万円 それ以外の人 最大250万円 |
シニア・障がい者向け制度
高年齢雇用継続給付金
60歳の定年後も同じ会社で働き続ける人が受け取れる給付金。
定年後に働き続ける人の給与が下がった場合、差額の一部を補填。
| 条件 | 雇用保険の被保険期間が5年以上ある 60歳以上、65歳以下 雇用継続を受けた後の給料が以前の75%未満になる |
| 支給額 | 最大で雇用継続後の給料の15% |
| 支給期間 | 65歳になるまで |
高年齢求職者給付金
65歳以上の高齢者が離職して失業状態となった場合にもらえる給付金。
| 条件 | 雇用保険の被保険者 積極的に求職活動をしている 年金の受給との併用は可能 |
| 支給額 | 賃金日額 × 給付率(50〜80%)× 給付日数 |
| 支給日数 | 雇用保険の被保険者であった期間が、 1年未満 → 30日分 1年以上 → 50日分 |
高年齢再就職給付金
60歳以降に他の職場に再就職した人が受け取れる給付金。
| 条件 | 雇用保険の被保険期間が5年以上ある 60歳以上、65歳以下 60歳以上で退職後に失業保険を受け取り 再就職した時、失業保険の残日数が120日以上ある 雇用継続を受けた後の給料が以前の75%未満になる |
| 支給額 | 最大で雇用継続後の給料の15% |
| 支給期間 | 65歳になるまで |
福祉タクシー利用券
障がい者や高齢者向けに、通院・買い物用タクシー代の一部を補助。
| 条件 | 各種障害者手帳を交付された方 |
| 支給額 | 年間2〜4万円程度 |
介護保険住宅改修費補助
高齢者が転倒予防&介護の軽減等のために住宅回収する時、工事費用の一部が助成される制度。
| 条件 | 65歳以上の方が住んでいる 持ち家であること 工事前に自治体に認定 |
| 支給額 | 20万円の現金給付 |
災害・トラブル時の支援
雑損控除
なにかアクシデントがあって資産が損なわれた場合に適用できる所得控除。
確定申告で控除する。
- 災害による損失(地震、雷、火事、冷害、風水害など)
- 盗難、横領など(詐欺や恐喝は対象外)
| 条件 | 警察に盗難届を出し証明書をもらう 災害の場合は消防署で証明書をもらう |
| 控除例 | 損失額 – 総所得×10% 例) 100万円 – 200万円×10% = 80万円 の所得税が安くなる ※1年で控除しきれない分は3年間繰り越せる |
災害障害見舞金支給制度
自然災害が原因で重い障害を負ってしまった場合に受けられる。
| 支給額 | 生計を維持していた人 最大250万円 それ以外の人 最大125万円 |
葬祭費・埋葬料補助金制度
故人が健康保険等に加入していた場合、葬式後に葬儀をした方が申請すると補助金が受け取れる制度。
| 埋葬費補助金制度 | 葬祭費補助金制度 | |
| 故人の加入保険 | 社会保険 各種共済組合 | 国民健康保険 後期高齢者保険 |
| 申請先 | 各種健康保険 | 市区町村の保険年金課 |
| 補助金 | 5万円 | 3〜7万円 |
※故人が死亡してから2年以内に申請
自治体の隠れ補助金
『自治体+補助金』で検索すると、意外な支援が見つかります。
スズメバチ等の巣 駆除費用の補助制度
スズメバチ等の巣を駆除処理された方に補助金が交付される制度。
| 条件 | スズメバチ&ミツバチなど駆除してから1ヶ月以内に申請 |
| 支給額 | 1〜2万円程度 |
| 注意点 | 対象となる蜂の種類は自治体による 自治体の指定業者でなければならない |
生ゴミ処理機等購入の助成
家庭用電動生ゴミ処理機等の購入費の一部が助成される制度。
| 条件 | 自宅用に購入した場合 |
| 支給額 | 2万円程度 |
| 注意点 | 購入前に申請が必要な場合もある |
みどりの補助金
自宅や土地を緑化した人に、その緑化費用の一部を補助するCO2削減等を目的とした制度。
| 条件 | 新たに緑化する面積が◯◯㎡以上 完了報告書の提出をすること 一定年数後の経過報告をすること |
| 支給額 | 10万円〜数百万円 |
チャイルドシート購入助成
子供がいる世帯に助成金、レンタル、不用品譲渡などいろいろ。
| 条件 | 自治体により様々 ご自分の住まいの自治体に確認 |
| 支給額 | 3,000円〜10,000円 |
特定優良賃貸住宅の家賃・住み替え助成金
月数万円の家賃補助 × 最長20年間
地方移住歓迎の自治体
月◯◯万円の家賃補助 × ◯◯年間
まとめ|“申請した人だけ”が得をする!
制度は年々変わりますが、共通しているのは「申請しないともらえない」という点。
該当しそうな制度を見つけたら、早めに役所・保険組合に相談しましょう。
🔍 検索のコツ:「自治体名+補助金」「制度名+申請」
🧾 証明書類(領収書・診断書など)は必ず保管
💡 一度使える制度を知っておくと、家計の安心感がまるで違います!